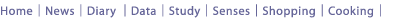NEW
レゴが大好きだったお父さんが、
今度は息子と一緒に夢中になれる新商品がでた!
(2001.1.10)
|
 |
ブロック玩具のレゴジャパン(R)は、2000年9月に教育用ロボットのラーニングシステム「ROBOLABOホームラーニング・キッド」の販売を開始した。それは、自分のパソコンを使ってプログラミングして、ブロックを動かす、といった高度なもの。世界的な教材メーカーであるレゴグループと米国マサチューセッツ工科大学の永年の研究成果にもとづき開発された。この「ROBOLABホームラーニング・キッド」は、すでに数多くの教育機関で導入されており、各分野での教育の推進に貢献している。
また、今年1月9日発売予定の「レゴ ライフオンマース」は、幼年向けの遊び中心のブロック。このシリーズは、火星が舞台で新世紀にふさわしく大きいテーマとなっている。
レゴの商品は、現在30〜40代のパパが子供の頃に触れてきた、わくわく感のある夢のあるものばかり。自分の子供に、レゴのロボットが与えられる時代になったとは!パパたちもまた、少年時代にフィードバックできそうだ。
http://www.lego.com
http://www.mdstorm.com
(R) LEGO is trademark of the LEGO Group. (C)2001 the LEGO Group.
|
「News Week」2000. 12.13号では、子供の0歳教育第二弾を特集!
赤ちゃんの脳を科学しながら、子育てすることが重要。
(2000.12.30)
|
 |
赤ちゃんの脳には約3兆のシナプスがあるが、大人になるまでに
ほぼ半数が消滅し、繰り返し使われたものだけが恒久的な回路と
なる。シナプスを固める協力な「接着剤」になるのが、達成感や
誉め言葉でのフィードバックだ。ボールを追いかけてハイハイした
とき、「すごいねえ」とママが言えば、ハイハイの動きに関連した
ニューロンの結合は強化される。それ以上に子どもの自信を支える
のは、自我の芽生えだ。生後4か月ごろには、鏡に映った自分を見て
にっこりするようになる。だが、この段階ではまだ自意識はないらしい・・・。
と、最近の「News Week」では、育児記事が目立っています。
男性読者が多い雑誌ですが、このテーマに関心が高いからこその特集
だと思われます。育児をジャーナリスティックに取り上げると、男性
にも興味をもってもらえるのですね。
http://www.nwj.ne.jp |
アエラ別冊「子育ては損か?」は、
2118人の投稿e-mailから構成された大激論本!
[So Da Tsu comも、おススメサイトで紹介]
(2000.12.30)
|
 |
“子育ては損か?”この特集が「アエラ」の紙面に載った瞬間、
大激論が始まった、と言われます。「アエラ」のネット上で
「インタラクティブ」欄を設けたところ、読者と編集の双方向
のやりとりが始まりました。そのダイジェスト版がこの本です。
このテーマについてのアンケートでは、面白い統計がでており、
最初の一週間に届いた119通のうち、「子育ては損」という意見は
45%。その内容が興味深い。
「損だ」と答えた中で「条件や環境が改善されたら、もっと
子どもが欲しい」「子どもを産んでよかった」と書いた人が
いずれも
7割、「産まない方がよかった」という人はゼロ。
多くの人が子どものいる喜びや充実感をつづっていて、そこだけ
読むと、その人が「損」と感じているとはとても思えないほどです。
まして「得するのなら育てる」と主張する人など1人もいなかったとか。
http://opendoors.asahi-np.co.jp/span/aera/rz20001215.htm
http://opendoors.asahi-np.co.jp/span/aera/survey_archive.htm
「子育は損か?」に参加した読者が議論しているメーリングリスト
http://www.egroups.co.jp/group/i-kosodate
|
日本小児保健協会では、「マタニティーブルーと産後の抑うつ症状」を研究。出産は、最大のストレスか?
(2000.12.21)
|
 |
マタニティーブルーは、一過性の軽度のうつ症状のこと。分娩後の内分泌の急激な変化が一因であり、分娩後の1〜2週間で回復し、特に医学的な治療は必要ないとされている。
しかし、今回の研究結果で注目されるのは、産後6カ月〜13カ月においても、疲労自覚症状や育児不安が高かったことである。つまり、周産期から育児期までの母子保健をトータルに考えていかないと、育児ストレスも高くなり、心身の不調を訴えることが永続的になるというのだ。継続的な看護、個別
の育児相談など、広い意味での育児支援が望まれる、とのこと。 参考資料/『小児保健研究』産褥早期から13ヶ月の母親の疲労に関する研究 服部律子(岐阜県立看護大学、助産婦)中嶋律子(名古屋市立大学看護学部、助産婦)発表
http://plaza.umin.ac.jp/~jschild/ |