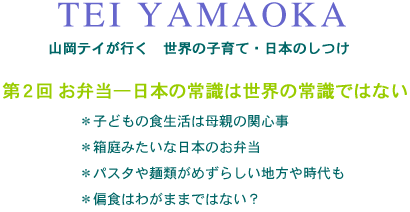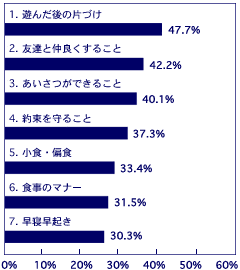■子どもの食生活は母親の関心事
幼児をもつ母親を対象に、育児の気がかりを調査すると、必ず上位に「食べ物の好ききらい・少食」や「遊び食べなど食事マナー」など食生活の悩みがあげられる。(図1)
野菜をいやがる、肉や魚を食べない、スナック菓子や甘い飲料水は大好き、嫌いなものを食べるときは、遊び食べやテレビを見ながらで、親がせかせて口に持っていかないと食べないなど、心配はつきない。偏食や少食は、園や学校へ通い始めたら、お弁当や給食が食べられるかしらと、つい先の心配をしてしまうのが親心。その上、農薬や食品添加物、ダイオキシン、O-157や食中毒も含めた「食の安全性」も気になる。
 |
|
| オーストラリアの保育園での昼食風景。大きなバスケットにパンやお菓子を詰めてくる。 |
|
|
■箱庭みたいな日本のお弁当
日本に住み始めた外国人の母親が驚くのは、幼稚園の手づくりお弁当。
から揚げ、ハンバーグ、卵やチーズに加えて緑黄食野菜やプチトマト。ご飯にはカラフルなふりかけや海苔。見た目にもきれいで栄養バランスも満点。でも、こんなに手のこった、まるで、箱庭のようなお弁当が園の食卓に並ぶのは、他の国ではお目にかかれない。
私が海外の幼稚園や保育所で撮影したビデオでの食風景を日本で見てもらうと、「ハムサンドだけなの?」とか、「ご飯に麻婆豆腐をかけただけ?」と、いつも驚かれる。
「うちの園でも肉まん1個だけ遠足に持ってきた中国の子がいたわよ」という声もあった。
でも、肉まんは野菜やお肉が混ざり合い、サンドイッチも中身がいろいろ楽しめる、日本のおむすびみたいに便利でおいしい携帯食なのだ。
おむすび、肉まん(包子)、サンドイッチは、世界のお弁当業界(?)では似たような存在で、いわば、お母さん役ともいえる。そして、日本のすばらしくリッチなお弁当のバリエーションやお弁当用冷凍食材の品揃えは、少々行き過ぎ。日本の常識は世界の常識ではない。
■パスタや麺類が珍しい地方や時代も
アメリカやヨーロッパなどパンが主食の国ではサンドイッチが多い。中国では、「北麺南飯」といって、南はお米のご飯が主食で、北の地方は小麦粉系の包子や麺類、クレープ、餃子が中心となり、同じ国でも地域差がある。
つい10数年前のこと、マレーシア系オーストラリア人の友人が、子どものお弁当に焼きそばを持たせたら、「ワーイ、虫だ。虫をお弁当に持ってきているよ」と、クラスの子達に言われて、2度と麺類のお弁当は作らなくなったとか。いまや、焼きそばはオーストラリア人にとってもポピュラーなアジア料理のひとつになり、しっかり市民権を得ている。
いろいろな国で、園のお弁当や給食を眺めていると、お弁当にはおふくろの味があって、親の出身国の郷土料理がメニューの中心になっている。そして、親と離れて食べる昼食の時間を、子どもが少しでも喜んで過ごして欲しいという願いが込められているようだ。
■偏食はわがままではない?
最近は、食物アレルギーが一般的に知られるようになった。食べ物の好ききらいは、単に子どものわがままではなくて、体が拒否しているサインであり、体質的に受けつけない場合もある。食べ物の好みも個性のひとつで、好ききらいは成長とともに変化し、なにかのきっかけで食べられるようになることも多い。
偏食や少食で困ったときは、食卓や台所で調理を工夫するのも大事だが、子ども同士が大勢でワイワイ食べられる場など、思いっきり遊んでお腹が空く時間をもつことのほうが、より解決に近づく方法だ。
おわり
|